赤血球溶血のためのRBC lysis bufferの組成
RBC lysis buffer
NH4Cl 8,024 mg/l
KHCO3 1,0 mg/l
EDTA Na2·2H2O 3.722 mg/l
in MilliQ water
pH 7.3
赤血球を溶血させる実際の方法
マウスの全血約50ulに500ulのRBC lysis bufferを入れて、10分静置する。
濁度が低下すれば、赤血球は溶血しています。
4℃ 250 x gで10分間遠心し、上清を捨てる。
必要に応じ(よりきれいにしたい時は)もう一度RBC lysis buffer を加えて遠心、上清を捨てる。
遠心して得られたペレットはPBMC+血小板ですので、
FACSやDNA抽出などに使うことができます。
原文はこちらです。

The separation of different cell classes from lymphoid organs. V. Simple procedures for the removal of cell debris. Damaged cells and erythroid cells from lymphoid cell suspensions - PubMed
The separation of different cell classes from lymphoid organs. V. Simple procedures for the removal of cell debris. Dama...
赤血球が溶血する原理
赤血球だけ破裂して、他の血球にはほとんど影響がないって不思議だと思いませんか?
塩化アンモニウム溶液でなぜ赤血球が溶血するのでしょうか?
この原理について書いてあるサイトはほとんどなかったので、論文を検索してみました。
他にもっとよい論文があるかもしれませんが、この原理に迫っているだろうと思われる論文を見つけましたので、時間のある方はこちらを参考にして下さい。
簡単に説明すると、RhAGというアンモニウムイオンのトランスポーターが大事みたいです。
全血にアンモニウムイオンが多く含まれる溶液を加えることにより、平衡を保とうとしてアンモニウムイオンを赤血球内に取り込みます。そのときに、H2Oが同時に入ってくるために膨張して破裂するという仕組みみたいです。

RhAGはほとんど赤血球系にしか発現していないので、他の血球には影響がないようです。

このサイトでは他にも色々な実験プロトコールや試薬の作り方についてまとめています。
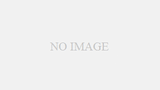
実験プロトコル
「実験プロトコル」の記事一覧です。
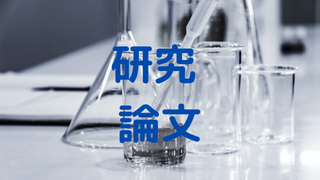


























コメント